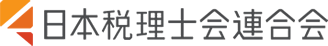登録に必要な提出書類等
主な提出書類等
申請に当たっての重要なご注意 ※必ずご確認ください
- ここに掲載している書類等は、提出書類等のうち主なものの案内となっております。税理士の登録手続き等の詳細については、「税理士登録の手引」をご参照ください。
- 税理士登録申請書一式は、税理士事務所又は税理士法人の事務所所在地を含む区域に設立されている税理士会へ提出します。
- 申請内容や提出先税理士会によって、手引きやここで案内している書類以外の書類の提出を求めることや、必要部数が異なることがあります。
- 申請書類を作成・準備される前には必ず提出先の税理士会ウェブサイト等で手続きの詳細を確認してください。(参考:全国の税理士会)
- 申請書類に不足や不備がありますと申請の受付ができなくなりますのでご注意ください。
- 申請書類の書式を印刷する場合は、全て白のA4コピー用紙に片面印刷してご使用ください。
※令和3年9月1日に施行された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に伴い、令和6年5月27日に改正税理士法施行規則が施行され、税理士名簿に登録を受けなければならない事項に個人番号が追加されました。また、令和7年6月30日より、マイナポータルからマイナンバーカード(有効な電子証明書が格納されているもの)を利用して登録免許税をオンライン支払サイトからクレジットカード払いすることが可能となりました。これを受け、税理士登録申請書(第1号様式)が改訂されていますのでご注意ください。
全申請者が提出を要する書類等
| No. | 書類等名称 | 必要部数 |
|---|---|---|
| 【1】 | 税理士登録申請書(第1号様式)[PDF/254KB]A4用紙で4-1、4-2、4-3、4-4の4枚となっています。A4片面印刷してご使用ください。 | 解説に記載 |
| 【2】 | 登録免許税領収証書(6万円) 又は、税理士登録申請に係る事前届完了通知書 ※登録申請書4-3に添付してください。 |
1通 |
| 【3】 | 登録手数料(5万円) | 納付 |
| 【4】 | 写真 | 3葉 |
| 【5】 | 身分(身元)証明書(本籍地の市区町村が発行したもの) ※詳細はページ下部掲載の「主な提出書類等の解説」でご確認ください。 |
1通 |
| 【6】 | 国籍の記載のある住民票の写し(外国籍の者のみ)コピーは不可 | 1通 |
| 【7】 | 資格を証する書類(原本との照合確認を受ける) | 1通 |
| 【8】 | 履歴書(第3号様式)[PDF/40KB] | 1通 |
| 【9】 | 誓約書(第4号様式)[PDF/84KB] | 1通 |
| 【10】 | 税理士会会長宛の誓約書[PDF/173KB] | 1通 |
| 【11】 | 直近2年分の確定申告書の一式 | 1式 |
| 【12】 | 税理士会が配布する日税連所定のはがき ※税理士会により受付時にお渡しする場合等取扱いは異なります。 |
1枚 |
実務経験期間の充足を確認する書類等(対象:試験合格者、試験免除者)
| No. | 必須書類 | 必要部数 |
|---|---|---|
| 【13】 | 在職証明書(第2号様式)[PDF/61KB] | 1式 |
| 【14】 | 在職証明書に係る印鑑登録証明書 | |
| 【15】 | 源泉徴収票又は確定申告書のコピー | 1式 |
| No. | 場合により提出する書類 | 必要部数 |
|---|---|---|
| 【16】 | 税理士事務所(税理士法人)と会計法人の関係について[PDF/64KB] | 1通 |
| 【17】 | 職務概要説明書[PDF/57KB] | 必要数 |
| 【18】 | 勤務時間の積上げ計算書[EXCEL/54KB] 勤務時間の積上げ計算書[PDF/180KB] |
必要数 |
| 【19】 | 大学院通学状況説明書[PDF/147KB] | 必要数 |
事務所の設置を確認する書類等(対象:開業税理士、新たに税理士法人を設立又は従たる事務所を設置する社員税理士)
| No. | 書類等名称 | 必要部数 |
|---|---|---|
| 【20】 | 税理士(法人)事務所の設置に関する書類 | 1式 |
その他必要に応じて提出する書類
| No. | 書類等名称 | 必要部数 |
|---|---|---|
| 【21】 | (勤務している又は勤務していた)会社の履歴事項全部証明書 | 必要数 |
| 【22】 | 無職期間の事情説明書[PDF/60KB] | 1通 |
| 【23】 | 退職理由説明書[PDF/32KB] | 1通 |
| 【24】 | 業務執行に関する誓約書[PDF/70KB] | 勤務先1社につき1通 |
| 【25】 | 退職同意書[PDF/62KB] | 必要数 |
| 【26】 | 旧姓使用承認申請書[PDF/84KB] | 1通 |
| 【27】 | 税理士法人の社員資格証明申請書[PDF/44KB] | 1通 |
| 【28】 | 社員税理士・所属税理士同意書[PDF/34KB] | 1通 |
| 【29】 | 税理士法人の定款(案)の写し | 1通 |
| 【30】 | 登録抹消した理由及び再登録する理由書 | 1通 |
| 【31】 | 早期退職の理由説明書[PDF/21KB] | 1通 |
このほかにも、登録調査の必要上、適宜の書類を提出していただく場合があります。
主な提出書類等の解説
全申請者が提出を要する書類等
- 税理士登録申請書(第1号様式)4-1、4-2、4-3、4-4
-
- 登録申請書の各欄は、黒色の万年筆又はボールペン(消せるボールペンは不可)で明瞭、正確に記入してください。訂正する場合は、修正液等は使用せず、二重線を引き、欄外に「何字訂正」あるいは「何字抹消、何字挿入」と記入してください。
- 登録申請書は下記にしたがって必要部数を用意してください。
4-1 申請事項記載書面・・・・・・5通
4-2 職歴記載書面・・・・・・・・5通
4-3 登録免許税領収書貼付書面・・1通
4-4 個人番号記載書面・・・・・・1通
※ 4-1、4-2については5通とも同一の記載内容とすることとし、全てに署名してください。正本以外の4通についてコピーでも差し支えありませんが、その際は正本の署名欄を空白にしたままコピーして正本とコピーのすべてに署名してください。
※ 4-4は必要事項の記入、マイナンバーカードのコピー(両面)等を貼付し、封筒(縦型 長形3号封筒等)に入れ、封筒に氏名を記入のうえ封緘して提出してください。 - 税理士となる資格又は税理士法第24条に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき内容を記載せず、もしくは虚偽の記載をして登録申請書を提出し、その申請に基づき登録を受けた者であることが判明した時は、当該登録が取り消されることとなるのでご留意ください。
- 登録免許税領収証書(6万円)又は、税理士登録申請に係る事前届完了通知書
- 税理士の登録には登録免許税の6万円を納付しなければなりません。納付方法により提出する書類等が異なります。
(納付書を使用して現金で納付する場合)
①国税収納機関(日本銀行、国税の収納を行う代理店、郵便局)で品川税務署あてに納付し、領収証書を登録申請書4-3に貼付します。納付書は税務署、一部金融機関で入手できます。取扱の有無は各所へ確認してください。
② 納付書は税務署、一部金融機関で入手できます。取扱の有無は各所へ確認してください。(マイナポータルからオンラインで支払う場合)
①マイナポータルからマイナンバーカード(有効な電子証明書が格納されているもの)を利用して、クレジットカードでオンライン支払いします。
②オンライン支払い完了後にマイナポータルから取得できる「税理士登録申請に係る事前届完了通知書」に支払完了日を記入し、登録申請書4-3に添付します。
③登録申請書4-4に「税理士登録申請に係る事前届完了通知書」に記載されている「申請ID」を記入します。※マイナポータルは国が運営する行政手続のオンライン窓口です。利用方法等はマイナポータルで確認してください。
・マイナポ―タル
https://services.digital.go.jp/mynaportal/
・マイナポータルマニュアル
https://img.myna.go.jp/manual/sitemap.html
・マイナポータルのよくある質問
https://faq.myna.go.jp/ - 登録手数料(5万円)
-
- 税理士登録の申請をするにあたり、登録申請者は日本税理士会連合会会則に基づき、登録手数料として5万円を納付しなければなりません。
- 当該手数料は、登録申請書を提出する際に税理士会の指定する方法(詳細は登録申請書を提出する税理士会HP等で確認してください)で納付します。
- 写真
-
- 申請書提出日前6月以内に撮影されたものを添付します。
- 以下の条件を満たしたものを提出してください
・申請者本人のみが撮影されていること
・上三分身であること
・背景は無地であること
・無帽で正面を向いていること
・サイズはおおむね縦3.0㎝、横2.4cm(運転免許証サイズ)であること - カラー、モノクロのどちらでも構いません。
- 写りが不鮮明なものや顔の部分が小さい等本人確認が困難なもの、また、粗雑な現像のため短期間で変色するようなものについては差替えを求めることがあります。
- 写真(3葉)の裏面に必ず氏名及び撮影年月日を記入してください。3葉のうち1葉は税理士証票に貼付します。
- 裏面のインクで写真が汚れることがあるので注意してください。
- 身分(身元)証明書(本籍地の市区町村が発行したもの)
-
- 当該証明書は、成年被後見人、被保佐人とみなされる者及び被補助人に該当しないこと(禁治産者、準禁治産者の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていないと表示されています。)、かつ破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。
- 当該証明書の発行申請書の記入にあたっては、上記の項目すべてを証明事項としてください。
- 申請書提出日前3月以内に発行されたものを提出してください。
- 外国籍の者は、身分(身元)証明書が発行されないため、「成年被後見人、被保佐人とみなされる者及び被補助人に該当しないこと、かつ、破産者でもない旨の誓約書」を提出します。
- 成年被後見人、被保佐人とみなされる者及び被補助人に該当しないことのいずれかについて証明されない場合は、「精神の機能の障害に関する医師の診断書」を提出します。
- 国籍の記載のある住民票の写し(外国籍の者のみ)
-
- 申請書提出日前3月以内に発行された世帯全員のものを提出します。
- 住民票の写しとは、市区町村の役所(役場)から発行された原本そのものを指し、そのコピーという意味ではありません。
- 住民票の写しは、個人番号の記載のないもの、個人番号の記載のあるものについてはマスキングをしてください。
- 外国籍の者については、前項の身分証明書に代えて誓約書の提出を求めているところ、誓約書を提出した者が外国籍の者であることを確認するために提出を求めるものです。
- 事務処理の都合からホチキス留を外して提出してください。
- 資格を証する書面
- 証明書以外の合格証書や通知書等の写しを提出する際に、税理士会にて原本照合を行います。詳細については提出先の税理士会に確認してください。
税理士となる資格 提出書類 (1) 税理士試験合格者 「税理士試験合格証書」(コピー) 特別税理士試験合格者 「特別税理士試験合格証書」(コピー) (2) 税理士試験免除者 「税理士試験免除決定通知書」(コピー) (3) 弁護士 日本弁護士連合会が発行した弁護士名簿に登録されている旨の「証明書」(原本)
※申請書提出日前3月以内に発行されたもの(4) 弁護士となる資格を有する者 - 最高裁判所が発行する司法修習生の修習を終えたことを証する証書(コピー)
- 法務大臣が発行する弁護士資格認定通知書(コピー)
- 最高裁判所が発行する最高裁判所の裁判官の職にあったことの証明書(コピー)
のいずれか1点(5) 公認会計士 日本公認会計士協会が発行した公認会計士名簿に登録されている旨の「登録証明書」(原本)
※申請書提出日前3月以内に発行されたもの(6) 公認会計士となる資格を有する者 <公認会計士試験改正前の場合> - 「公認会計士第3次試験合格証書」(コピー)
<公認会計士試験改正後の場合> - 「公認会計士試験合格証書」(コピー)
- 「実務補習修了証書」(コピー)※
- 「財務局長名による業務補助等の報告書受理番号を記した通知」(コピー)
の3点「修了考査合格証書」は不可 - 履歴書(第3号様式)
-
- 日税連所定の様式を用います。
- 「学歴」欄は、義務教育終了後の学歴を順に、入学及び卒業の年月日を記入し、昼夜の別を丸で囲みます。
- 「職歴」欄は、上部に就職年月日、下部に退職年月日(現在勤務中の場合は「現在」)を記入します。
- 「賞罰・免許・資格」欄に、必ず税理士となる資格を記入します。
- 誓約書(第4号様式)
-
- 税理士法第4条(欠格条項)及び第24条(登録拒否事由)に該当しないことを誓約するものです。
- 税金に未納がある者については、税理士法第24条第8号「税理士の信用又は品位を害するおそれがある者」に該当する疑いが生じることから、税理士登録を申請する前に完納してください。
- 再登録申請者で、過去に登録していた税理士会への会費未納が残っている者についても同様に税理士法第24条第8号に該当する疑いが生じることから、税理士登録を申請する前に完納してください(会費の未納は、税理士法第39条違反となります)。
- 日税連所定の様式に署名してください。
- 税理士会会長宛の誓約書
-
- 税理士法第38条(秘密を守る義務)、第41条の2(使用人に対する監督義務)、第42条(業務の制限)、第52条(税理士業務の制限)及び第53条(名称の使用制限)について遵守することを誓約するものです。
- 税理士会所定の様式に署名してください。
- 直近2年分の確定申告書一式
-
- 非違行為の有無や租税回避的行為の有無など、適正な申告納税が行われているかを確認するためのものです。
- 確定申告をしている場合は、税務署に提出したすべての書類(以下、確定申告書一式という)を提出します。
- 令和7年1月より申告書の控えに対する収受日付印の押なつが廃止されました。書面で確定申告している場合は提出事実の確認のため、下枠のとおり提出してください。
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)により申告した場合は、確定申告書一式と合わせて「受信通知」を提出します。
【受信通知の確認方法】
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/42.htm - 確定申告をする前に登録申請する場合、提出する確定申告書のコピーは、2年前と3年前分のものとなります。確定申告した後に登録申請する場合、提出する確定申告書のコピーは、1年前と2年前分のものとなります。
- 確定申告をしていない場合は、その代替として住民税の(非)課税(所得)証明書を提出してください。
【申告書等情報取得サービス】
https://www.e-tax.nta.go.jp/shutoku-service/index.htm - 住民税の(非)課税(所得)証明書は、通常6月くらいから前年分のものの発行が可能となることから、その前に登録申請する場合、提出する(非)課税(所得)証明書は、2年前と3年前分のものとなります。6月以降に登録申請する場合、提出する(非)課税(所得)証明書は、前年と前々年分のものとなります。
- 再登録申請の場合、登録抹消期間に非違行為を行っていないか確認するため、2年分を超える確定申告書一式又は住民税の(非)課税(所得)証明書の提出を求めることがあります。
- 通常、課税証明書と所得証明書は同じものを指しますが、自治体によっては証明書を区分し、発行する課税証明書に所得金額が記載されていない様式もあるので、その場合は、所得証明書等、所得の種類と所得の額が確認できる証明書の提出が必要です。
- 「給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収額の決定・変更通知書(納税義務者用)」は、給与収入以外の所得があっても反映されないので、課税(所得)証明書の代替となるものではないのでご注意ください。
ア 令和5年分までの確定申告書
(確定申告書に収受日付印がある場合)
・確定申告書一式のコピーを提出
(確定申告書に収受日付印がない場合)
・確定申告書一式のコピーに加えて、下記A~Cの方法のいずれかを提出
A 申告書等情報取得サービスにて取得した確定申告書一式
B 税務署に対する保有個人情報の開示請求にて取得した確定申告書一式
C 確定申告書一式のコピーと税務署の発行する納税証明書(その2所得金額の証明)又は
市区町村が発行する住民税の課税(所得)証明書イ 令和6年分以後の確定申告書
・確定申告書一式のコピーに加えて、下記A~Cの方法のいずれかを提出
A 申告書等情報取得サービスにて取得した確定申告書一式
B 税務署に対する保有個人情報の開示請求にて取得した確定申告書一式
C 確定申告書一式のコピーと税務署の発行する納税証明書(その2所得金額の証明)又は
市区町村が発行する住民税の課税(所得)証明書【申告書等情報取得サービス】
https://www.e-tax.nta.go.jp/shutoku-service/index.htm※還付申告(ふるさと納税による寄付金控除、医療費控除)であっても確定申告書のコピーを提出してください。
- はがき
-
- 税理士名簿に登録された場合に登録年月日及び登録番号を通知するものです。
- 宛先には自宅の住所を記載します。
- 切手の貼付は不要です。
- 税理士会が配布する日税連所定のはがきを用います。
税理士会によっては申請書受付時にお渡ししたものに記入のうえ提出してもらいます。
実務経験期間の充足を確認する書類(対象:試験合格者、試験免除者)
- 在職証明書(第2号様式)
-
- 税理士試験合格者及び試験免除者に求められる実務経験期間を充足していることを証明するものです。
- 日税連所定の様式又は官公署から発行される職歴証明書を提出します。
- 勤務先の代表者からの証明書を発行してもらってください。勤務先が税理士法人の主たる事務所又は従たる事務所のいずれの勤務であっても、当該税理士法人の代表者からの証明書とします。
- 税務官公署に在職した者については、税理士となる資格の如何にかかわらず、必ず税務官公署に在職した期間の職歴証明書を提出してください。
- 再登録申請の場合は原則として提出を要しませんが、必要に応じて提出を求めることがあります。
- 在職証明書のみで実務経験期間の充足の有無を判断することが難しい場合は、必要に応じて参考となる書類の提出を求めることがあります。
- 税理士事務所又は税理士法人に併設される会計法人に並行して勤務している期間の勤務実績を実務経験とする場合は、給与の支払いの有無に関わらず双方からの在職証明書を提出してください。
- 印鑑登録証明書(在職証明書の証明者のもの)
-
- 在職証明書の公証力を担保するためのものです。
- 申請書提出日前3月以内に発行された在職証明書に押印された印鑑の登録証明書を提出します。
- 勤務先の事情により印鑑登録証明書の発行を受けることができない場合は、その代わりとして「印鑑登録証明書が発行できない旨の事情説明書(在職証明書の証明者が作成)」を提出します。
- 再登録申請の場合は原則として提出を要しません。
- 税務官公署から発行される職歴証明書には、印鑑登録証明書の添付は不要です(公文書であり、これ以上の公証力の担保は不要であるため)。
- 源泉徴収票又は確定申告書一式のコピー
-
- 在職証明書等及び職歴証明書により証明した実務経験期間に給与が支払われていた事実を確認するため、源泉徴収票又は確定申告書一式を提出してください。
(確定申告している年分について)
・確定申告をしている場合は、確定申告書一式を提出してください。
・確定申告書一式の提出方法については、「【11】直近2年分の確定申告書のコピー」を参照してください。
・なお、「【11】直近2年分の確定申告書のコピー」で提出する確定申告書一式にて実務経験の給与が支払われていた事実を確認できる場合は省略できます。(源泉徴収票の提出に係る留意事項)
・源泉徴収票に記載されている就職又は退職年月日と在職証明書に記載されている就職又は退職年月日に差異がある場合、若しくは年末調整の記載が漏れている場合は、再発行された源泉徴収票を提出してください。
・現在の勤務先で実務経験を申請し、申請日現在の年度分を含めないと実務経験期間が満たされない場合は、源泉徴収簿の一人別台帳のコピー(勤務先代表の者の押印(在職証明書に押された印影と同じもの)が必要)を提出してください。 - 税理士事務所(税理士法人)と会計法人の関係について
-
- 税理士事務所と税理士が主宰する会計法人に並行して勤務している場合、若しくは、勤務している税理士事務所に会計法人が併設してある場合、あるいは、勤務している会計法人に税理士事務所が併設してある場合に申請者の所属、給与の支払い状況等を確認するためのものです。
- 会計法人の代表者、目的等を確認するために添付書類として登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請書提出日前3月以内に発行されたもの)及び株主名簿の提出が必要となります。
- 勤務先が税理士事務所ではなく、税理士法人である場合には「税理士法人と会計法人の関係について」を作成します。
- 税理士会が用意する書面を用いて作成します。
- 職務概要説明書
-
- 実務経験の充足を確認するうえで在職証明書だけで判断できないときに提出を求めるものです。
- 従事していた業務内容及び業務に占める会計業務の割合を詳細に記載してください。
- 勤務先の代表者の押印(在職証明書に押された印影と同じもの)が必要です。
- 税理士会が用意する書面を用いて作成します。
- 会社の組織図を添付してください。
- 勤務時間の積上げ計算書
-
- パート、アルバイト、派遣労働等で従事しており、正規の雇用形態の者(正社員)と比べて勤務日又は勤務時間が少ない場合、もしくは、正社員であったとしても勤務時間を短縮していた場合などに勤務時間数が実務経験期間の充足を確認するために提出を求めるものです。
- 税理士会が用意する書面もしくは指示する様式を用いて作成します。
- 勤務先の代表者の押印(在職証明書に押された印影と同じもの)が必要です。
- 出勤日数等を確認するためにタイムカードのコピー又は出勤簿のコピー(出退勤時刻が明示されている書類)もしくは給与支払台帳のコピー等で、勤務先の代表者が余白に押印(在職証明書に押された印影と同じもの)したものの提出が必要です。
- 大学院の通学状況説明書
-
- 実務経験として申請した会社等の勤務期間と並行して大学院又は大学に通学していた場合、会社等の勤務日数、勤務時間等への影響を確認するために提出を求めるものです。
- 税理士会が用意する書面を用いて作成します。
- 勤務先の代表者の押印(在職証明書に押された印影と同じもの)が必要です。
- 受講していた講義に印を付けたカリキュラム(時間割)及び成績証明書を添付します。
事務所の設置を確認する書類等(対象:開業税理士、新たに税理士法人を設立又は従たる事務所を設置する社員税理士)
- 税理士(法人)事務所の設置に関する書類
- 開業税理士となる場合、未設立の税理士法人の社員税理士として登録申請する場合に事務所の設置場所が実態を伴うものかを確認するために次の書類の提出を求めるものです。
| 建物の所有者 | 形態 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 申請者 | ― |
|
| 申請者を含む共有 | ― |
|
| 上記以外 | 使用貸借 |
|
| 賃貸借 |
|
|
| 転貸借 |
|
注1 未登記の建物に事務所を設置する場合は、登記事項証明書に代えて所有者、所在地、床面積等を確認す
るため、市区町村が発行する固定資産関係の証明書(例:公課(公租)証明書、固定資産評価証明書、
固定資産課税台帳の写し 等)を添付してください。
注2 登記名義が異なる場合は変更してください。
注3 不動産登記法の改正によって令和8年4月から住所等変更登記が義務化されます。住所が異なる場合は
注意してください。
注4 建築中の物件に事務所を設置する場合は、建築確認申請書のコピー(建物の完成予定日が記載されてい
るもの)の提出が必要となりますが、税理士(法人)には事務所を設置する義務があることから、税
理士登録完了日までに建物の引渡証又は登記事項証明書を提出しなければなりません。
注5 建物の登記事項証明書が地番表示となっており、事務所設置場所の表記(住居表示)と異なる場合は建
物全部事項証明書の所在地と住居表示の違いについて書面を提出してもらう場合があります。
注6 税理士事務所を賃貸借する場合は、税理士登録した時点で税理士事務所が設置されていなければならな
いことから、事務所の賃貸借契約の開始時期に注意してください。なお、税理士登録前に締結する賃
貸借契約において「税理士」といった文言を使用することは避けてください。
注7 税理士登録と同時に新たに税理士法人を設立又は従たる事務所を設置して社員税理士となる場合、税理
士事務所設置同意書の「建物の所有者」欄に申請者との関係性を記入してもらいますが、「申請者」
には、新たに設立する税理士法人の申請者以外の社員予定者を含むことに留意ください。
注8 建物の管理責任者等からの「税理士事務所設置同意書」については税理士会が用意する書面を用いて作
成し、上表の建物の状況に応じて同意者や所有者の署名をもらってください。署名すべき者を騙って
他人が署名したものを提出した場合、偽造有印私文書の行使となるおそれがあるため注意してくださ
い。建物が居住用で管理組合から同意が得られない等の場合は、税理士会が用意する「税理士事務所
設置に関する誓約書」に署名してください。
その他必要に応じて提出する書類
- 会社の履歴事項全部証明書
- 次の場合に必要となります。
- 申請者が会社の取締役、相談役、監査役など役員の場合、又は税理士事務所と並行して会計法人に勤務している場合(同法人の業務内容(目的)を確認し、非違行為の有無を確認するため)。
- 在職証明書を発行するべき会社が在職中あるいは退職後に吸収合併により消滅している場合(会社の吸収合併を確認するため。この場合、申請者が勤務していた会社を吸収合併した会社(存続会社)の履歴事項全部証明書を提出します。)
- 在職証明書を発行する会社が申請者の在職中あるいは退職後に名称もしくは所在地を変更している場合(会社の名称もしくは所在地の変更を確認するため)。
- 無職期間の事情説明書
-
- 職歴に長期の無職期間(原則として申請日前5年以内に6月以上)がある場合、非違行為の有無を確認するために提出するものです。
- 無職であったことを確認するため、その期間の住民税の課税(所得)証明書の提出を求めることがあります。
- 税理士会が用意する書面を用いて作成します。
- 退職理由説明書
-
- これまでの職歴において、短期間に退職(転職)を繰り返している場合、その理由が税理士法第24条第7号(心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠くおそれがある者)もしくは第8号(税理士の信用又は品位に害するおそれがあり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者)に該当しないか確認するために提出を求めています。
- 税理士会が用意する書面を用いて作成します。
- 業務執行に関する誓約書
-
- 他の会社等で勤務をする場合に勤務先で税理士業務を行わないこと、また、会社等で税理士業務を行わせないことを誓約するものです。
- 常勤・非常勤といった勤務形態や監査役といった職務形態に関わらず、他の会社等で勤務する場合や予定する税理士事務所とは別の場所で他の士業事務所を運営する場合は提出が必要になります。
- 税理士会が用意する書面に自身で署名するとともに、勤務先代表者の署名又は記名(ゴム印等)及び登録印による押印をもらってください。
- 証明すべき者を騙って他人が署名したものを提出した場合、偽造有印私文書の行使となるおそれがあるため注意してください。
- 退職同意書
-
- 現在勤務している会社等を税理士登録するのを契機に辞める場合、会社等から退職の承諾を得ていることを確認するためのものです。
- 税理士会が用意する書面に勤務先代表者の署名又は記名(ゴム印等)及び登録印による押印をもらってください。
- 証明すべき者を騙って他人が署名したものを提出した場合、偽造有印私文書の行使となるおそれがあるため注意してください。
- 旧姓使用承認申請書
-
- 婚姻等の理由により氏が変わった者については、当該書面を提出することにより、婚姻等の前の氏を税理士の業務で使用することができます。
- 旧姓を使用することが承認された場合に税理士の業務上で使用する姓は、すべて旧姓となります。
- 旧姓使用承認申請書に記載された旧姓については、国家資格等情報連携・活用システムを使用して確認するため原則として添付書類は不要となりますが、戸籍上の氏に変更が生じた日が平成14年8月4日以前(住民基本台帳ネットワークシステムの稼働が開始する前)の場合は、戸籍上の氏名及び旧姓の記載がある戸籍抄本又は個人事項証明書(申請書提出日前3月以内に発行されたもの)を添付してください。
- 税理士法人の社員資格証明申請書
-
- 税理士法人の社員税理士となるためには、税理士法人の社員としての登記が必要となり、法務局へ登記申請する際の添付書類である「税理士法人の社員資格証明書」の発行を申請するものです。
- 社員税理士となる場合には必ず提出します。
- 登録手数料とは別に発行手数料として1通あたり1,200円が必要となります。
- 社員税理士・所属税理士同意書
-
- 税理士法人の代表者又は開業税理士が、申請者を社員もしくは所属税理士とすることに同意していることを確認するために必要となるものです。
- 税理士法人の主たる事務所又は従たる事務所のいずれに登録する場合においても、当該税理士法人の代表者からの同意が必要となります。
- 同意書には税理士又は税理士法人の登録印による押印が必要です。
- 税理士会が用意する書面を用いて作成します。
- 税理士法人の定款(案)の写し
- 税理士登録と同時に新たに設立する税理士法人の社員税理士になる場合、設立予定の税理士法人の内容を確認するために必要となるものです。
- 登録抹消した理由及び再登録する理由書(再登録申請者のみ)
-
- 登録抹消後の非税理士行為の有無を確認するために必要となるものです。
- 書式は自由ですが、登録抹消した理由、登録抹消後の動向、登録抹消時の顧問先の動向、再登録する理由は必ず記載してください。なお、登録調査の過程で必要に応じその他事項の説明書や確認資料等の提出を求めることがあります。
- 早期退職の理由説明書
-
- 税務官公署を定年前に退職して税理士登録申請する者に提出を求めるものです。
- 税務官公署での勤務において非違行為がなかったかを確認するために必要となるものです。
- 税理士会が用意する書面を用いて作成します。